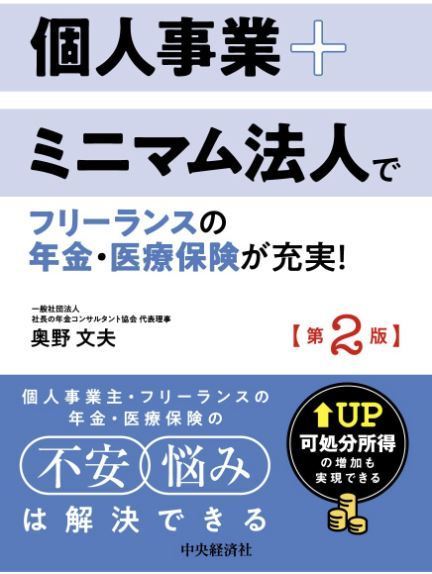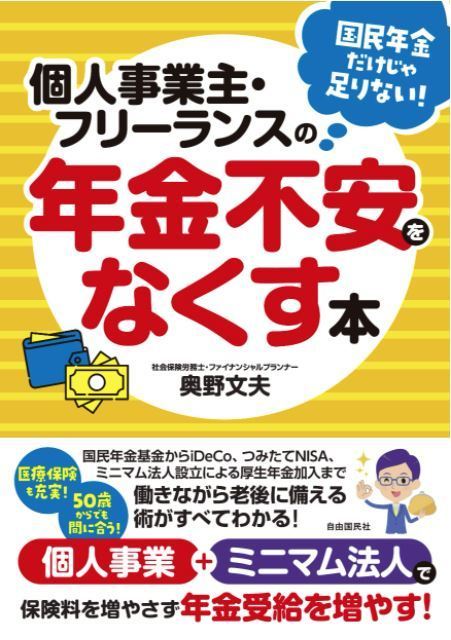60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
|---|
FAX | 077-578-8907 |
|---|
令和6年(2024年)からの新しいNISA制度とフリーランス・個人事業主・小規模企業経営者等の投資・資産運用
新しいNISAに関する雑感
令和6年から始まる新しいNISAが注目を浴びており、インターネット上等で様々な情報が提供されています。
全ての方に対して株式投資等をおすすめしているわけではなく、個別の運用手段や銘柄に関する助言等も行なってはおりませんが、自身の経験談も踏まえた雑感を以下に記載いたします。
(もし株式投資を行われる場合は、投資元本よりも基準価額・評価額が下がる可能性も当然ありますので、余裕資金の一部だけを用いて、あくまでも自己責任で行うようにしてください)
新しく投資を始める初心者の方(得に40代以下の方)は、一般的には、やはり、
1.全世界株式インデックス投資信託一本で長期(20年以上)・分散・積立投資を行うのが無難なケースが多いでしょう。
令和5年末までの現行のつみたてNISAでは年40万円までしか積立できませんが、余裕資金があれば、来年からの新しいNISAでは年間非課税積立額をもっと多くすることもできます(年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円・成長投資枠が240万円。現行のつみたてNISAで購入できる投資信託であれば、つみたて投資枠でも成長投資枠でも購入できるようになりますので、最高で年間360万円(毎月積み立てなら最高30万円まで)積み立てられます)。
なお、非課税保有限度額(総枠)は1,800万円(内、成長投資枠1,200万円)です。
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html
50代くらいの方が(1.全世界株式インデックス投資信託を行った上で)、もし投資先を検討する時間や株価暴落によって半分以上なくなっても大丈夫な余裕資金があるのであれば、
さらに、次の運用手段のうちご自身の資産形成目的・運用目標、リスク許容度や性格に合ったものも適宜入れてみるという選択肢も考えられます(これらも基本的に長期保有が前提です。下記(特に4や5は)定期購入ではなくて、株価が暴落したときなど株価が下がって有利な条件で購入できるときに購入するのが基本です)。
2.全世界株式インデックスや米国株式インデックスに連動した東証ETF
3.全世界株式インデックスや米国株式インデックスに連動した米国ETF
4. 米国連続増配株・高配当株ETF
5.国内安定増配(累進配当)株(個別株)への投資
など
私(奥野)自身は、社会人になってからの30年ほどは預貯金等が中心でしたが、50代半ばになってからつみたてNISA年40万円(月33,333円)で1の積立をはじめ、また、上記の2~5や米国債券ETF、米国以外の先進国株・新興国株なども課税口座(特定口座)で複数の商品・銘柄を徐々に購入してきました。
令和6年からは新しいNISAを活用して、「つみたて投資枠」で1の長期・積立・分散投資を継続しつつ、その他にも「成長投資枠」で適宜買い増ししていこうと思っています(成長投資枠で購入できないものは引き続き特定口座で購入)。
私の場合は仕事柄、自分がよい・面白い・性格に合っていると思う方法で運用・投資を行った成功体験・失敗体験が書籍・雑誌やメルマガ等の執筆ネタ、セミナーネタになります。
また、顧問先社長等からの一般的な質問に対応できるようにとの考えで、多くの方が行っている一般的な運用については理解できるように、継続的に実践してみておくことにもしています。(したがって、前記のもの以外に、個人向け国債(変動10年)・米国債や米国株式インデックス投信もある程度は持っています)
しかし、これから投資を始める方等の場合は、以下の点を常に念頭に置いていただくのが安全かと思います。
・令和6年以降、新しいNISAを活用する場合も、投資はあくまでも余裕資金で無理のない範囲で行うのが大原則であることは、今と変わりありません。
・投資した後に株価が半分以下に下がったとしても我慢できる・最悪なくなってもよいと思える場合以外は、(特に50代以降の方は)特定の少数の個別株への一括投資は行わない方が無難だと思います。
個別株に投資する場合も最初は、1株から購入できるネット証券(1株購入でも購入時に手数料がかからないネット証券会社もあります)でご自身のリスク許容度を踏まえて少しずつ購入するのがよいケースが多いでしょう。
個別株投資を行う場合は、リスク管理のためにセクター(業種)分散・銘柄分散も重要です。
・個人事業主・フリーランス・小規模企業経営者は、今もし余裕資金がなかったとしても、本業(または新規事業・副業で)毎年の可処分所得を確実に増やし、無駄なお金を使わず、貯蓄を数年続ければ、焦らなくてもいずれ余裕資金を使って落ち着いて投資を行える状態となります。
余裕資金を十分持っていれば、株価が上がることが予想される局面で効果的(割安)に投資を行うこともできます。
足元の余裕資金も固まっていないのに、NISA枠が増えるからとにかく非課税枠を最大限使わねば、との考えで投資金額を無理に増やすのは危険です。
・個人事業主・フリーランス・小規模企業経営者は、最低2年程度は売上ゼロとなったとしても生活できる現金・預金(や国債)を持っておきたいです。
(「2年」という数字は、個々人の価値観・家族構成・生活費等に応じて一人一人異なりますので、ご自身の場合に安心できる期間に置き換えて考えてください)
・その他、数年後に使途が決まっているお金にも手を付けずに残しておく必要があります。
年金・退職金・資産運用の基礎知識についてセミナー講師を務めました
令和5年2月16日(木)17時から、ZOOonline様のウェブセミナーにて、中小企業経営者の公的年金、役員退職金、資産運用の基礎知識について奥野がお話させていただきました。
https://zuuonline.com/archives/243429
主催者様からは、「参加者のお声でも非常に評価を頂戴しておりまして、専門性が高く、もっと話を聞きたいということで、皆様の満足度が高かったです」とのお声もいただきました。
当日参加できなかった社長様から個人的にご要望をいただきましたので、私どものメルマガでご参加希望者を募った上で、同様の内容について令和5年3月17日(金)17時~18時までZoom(自社開催)にて再度お話しいたしました。
2024年からの新NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)と50代・60代の中小企業オーナー社長の資産運用
高額報酬を受けている年金受給世代の中小企業オーナー社長(厚生年金保険の被保険者または70歳以上被用者)であっても、役員報酬設定を変更することで、役員報酬年額を下げずに働きながら老齢厚生年金を受けられるようになります(年金復活プラン)。
これにより、役員報酬年額は現状と同じであっても、毎事業年度会社に残るお金(営業利益)は増え、毎年の本人の手取り収入(給与・年金を合計した可処分所得)も増えます。
会社に残すお金と本人に残るお金の割合は、毎事業年度の役員報酬設定により、自由に決めることができます。
会社に残すお金100%・本人に残るお金0%でも、会社に残すお金50%・本人に残るお金50
%でも、自由に設定できるということですね。
もちろん、会社に残すお金0%・本人に残るお金100%とすることもできます。
会社・本人にどのような割合でお金を残すかは、会社・本人が何のために役員報酬設定を変更した
いのかにより決めることとなります。
会社で事業のために自由に使えるお金を増やしたいのであれば、会社に残すお金の割合を増やすことになります。
一方、本人が自由に使えるお金を増やしたいのであれば、本人に残るお金の割合を増やすこととなります。
会社に残すお金、本人に残るお金のいずれについても、具体的な使いみちは自由ですし、各会社・各経営者によって、様々な使いみちを想定できると思います。
例えば、毎事業年度会社に残したお金から法人税等を引いた残りは役員退職金原資として貯めることもできます。
一方、本人に残したお金は、預金や債券として貯めることもできますし、2024年から始まった新NISA
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html
のつみたて投資枠や成長投資枠を活用して投資をして増やそうとすることもできます。
ただ、投資信託やETF、個別株への投資は、増える場合だけでなく、減る場合もありえます。
NISAは配当金・分配金や売却益が出ても非課税というとても有利な制度(非課税限度額は1,800万円)です。
その有利さを有効活用するためには、安定して増える可能性が高い投資を行う必要があります。
(NISAでは、損失が出た場合の損益通算もできません)
ですから、60歳以上の方が新NISAを活用する場合であっても、ある程度長期投資を想定して
活用するのが無難です。
●つみたて投資枠について:一般論
私(奥野)は、50歳程度以下の方であれば、全世界株式インデックス投資信託(実績があり、信託報酬が安く、純資産総額が大きいもの)に余剰資金から毎月等定期的に積み立てていくのが無難だと考えています。
50歳以下の経営者であれば、毎月10万円・年間120万円×5年で600万円積み立てを検討している方もおられるかもしれません。
●つみたて投資枠について:60歳以上経営者向け一般論
60歳以上の方であっても、15年程度以上積み立て投資ができる(15年程度以上使う予定がないお金がある)のであれば、同様に余剰資金から全世界株式インデックス投資信託に毎月等積み立てるのもよいと考えています。
15年以内に使う予定がある、途中絶対に資産を減らしたくない、15年以内に元本を割っているのをなるべく避けたいということであれば、つみたて投資枠の利用はせずに預金・債券で貯める、とか、つみたて投資枠の利用割合を減らし、預金・債券の割合を増やす方がよいでしょう。
●成長投資枠について:一般論
50歳以下程度の方で、毎月10万円を超えて投資できる場合は、成長投資枠でも、余剰資金から
全世界株式インデックス投資信託を購入しても構いません。
50歳以下の経営者で、個別株の銘柄選定等に時間をかけずに仕事に集中したい、というようなケースであれば、年間240万円×5年で1,200万円(成長投資枠の上限)、全世界株インデックス投資信託への投資を検討している方もおられるかもしれません。
つみたて投資枠は最低でも年2回以上に分けて積立てすべきところ、成長投資枠では年間何回投資しても構いません。
ですから、年初に1回投資したり、当面は毎月投資しておき株式相場が暴落したときにまとめて投資する、などの活用法も柔軟にできます。
もちろん、成長投資枠は使わずに、つみたて投資枠だけを使うこともできます(この場合、例えば、
年120万円×15年で非課税限度額1,800万円をすべて活用することもできます)
●成長投資枠について:60歳以上経営者向け一般論
過去の株式インデックス投資信託に関するデータから、一般に、15年程度積み立てたら元本を割ることはないだろう、と説明されていることがよくあります。
ただ、過去のデータが今後もあてはまるかどうかはわかりませんし、15年程度以上も積み立てるのは長すぎる、15年程度積み立てたときに万一暴落が来たら、そんな中、投資信託を取り崩して生活費等に充てていく(か取り崩し金額を減らしながら暴落が過ぎるのを待つ)のは不安だ、と感じる方もおられるでしょう。
そんな場合は、成長投資枠は、例えば次のような比較的安定度が高いといわれることのあるタイプの投資を余剰資金で行うために使うこともできます。
・国内個別株(財務状況や利益状況が安定してよい大型高配当株・連続増配株に絞って、業種を分散して小額ずつ投資する)
・国内高配当株ETFや連続増配株ETFに投資する(信託報酬がかかってもよいから、個別株の銘柄選定に時間をかけたくない方の場合)
実績のあるETFで、なるべく信託報酬の少ないものから優先して検討するのがよいでしょう。
・実績のある米国高配当株ETF、連続増配株ETF(資産額が大きく、値動きが激しくなく、
経費率が低いもの)に投資する
つみたて投資枠での全世代型インデックス株式投資信託では分配金は再投資に自動的に回されるため、資産形成期の人には最適なのですが、60歳以上で資産形成期を過ぎていると考えている方の場合は、元本を減らさずに配当金や分配金を毎年確実に受けて、配当金・分配金の範囲で自由に使いたい、というニーズもあるでしょう。
そのような場合は、上記のような成長投資枠の活用の仕方も考えられます。
ただし、インカム(配当金・分配金)重視で、できれば含み益もある程度は増えていく方がよい、という考えで上記のような比較的安定した個別株投資やETF投資を行うにしろ、暴落時には保有資産が大きく減る可能性もあります。
ですから、そのようなときにも買い増せる、あるいは、暴落がおさまるまで落ち着いて待てる、という範囲の余剰資金で活用することが重要です。
もっとも、高額報酬の経営者の場合、もともと働きながら老齢厚生年金をもらうことはできない、と考えていた方が多いでしょう。
ですから、役員報酬設定を変更することで役員報酬年額を下げずに老齢厚生年金を受給できるようになり、その効果を本人に残すようにした場合には、毎年残るお金を、リスクを承知で成長投資枠を活用して非課税メリットを享受して資産を増やす可能性にかけてみることも、(もともとは受け取ることを想定していなかったお金と考えれば)それほど抵抗は感じずに済むかもしれません。
就業年数が伸びていること(経営者の場合は、後継者がいないなどの理由で事業承継が進んでいないこと)や、令和4年度から老齢年金を最高75歳まで繰下げできるようになったことなどから、65歳からの老齢厚生年金・老齢基礎年金を繰下げて将来受け取る年金額を増やすことが世間では注目されていますが、繰り下げないで65歳からこれらの年金をもらって投資に充てる、という選択肢もあるわけですね。
もちろん、投資は、先述のようになるべく安定を重視した方法を活用しても、暴落時には全体が下落
します。
また、インカムゲイン重視の場合、株式市場全体が暴落しているなど、優良銘柄をなるべく割安な状態で購入することが重要であるところ、例えば、日本の高配当株投資家・連続増配株投資家に人気の
ある銘柄は、2024年1月初め現在、高値圏にあるものが多いです。
多くの書籍等でおすすめ銘柄と書いてあるものであっても、現在は買い時とは言えない銘柄も多い
ことには注意が必要です。
投資をする・しないや、どのような方法でどのような銘柄・商品に投資するかは、自己責任により判断してください。
(以上、つみたて投資枠・成長投資枠の活用法の一部について概要を説明しました。一つの意見にすぎませんので、あくまでも参考、ご検討のためのきっかけ程度になれば幸いです。
50歳以上60歳未満の方は、現在の金融資産・今後のライフプラン、リスク許容度等により、お一人おひとり、50歳以下の方寄りの活用方法や60歳以上の方寄りの活用方法を自由に考えていただけるかと思います)
新NISA等については、希望される社長様が多いようでしたら、また情報提供することといたします。
2024年からの新NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)と50代・60代の中小企業オーナー社長の資産運用
(2024年9月6日)
2024年8月上旬に株価が大きく下がりました。
日経平均は7月中旬から下落基調でしたが、7月31日(水)39,101円から8月1日(木)38,126円、8月2日(金)35,909円と下がり続けた後、週明け8月5日(月)には31,458円と大きく下がり、8月6日(火)には34,675円まで反転して上がり、8月中旬からは38,000円前後を上下しました。
いつもお伝えしております通り、新NISA等を利用した投資を行うに際しては、基本的に次の2つのような、リスクを抑えながらの長期分散投資が無難だと考えています。
1.全世界株インデックス投信の長期積立
2.安定高配当株・連続増配株投資やETFによるインカム(配当金・分配金)の長期積上げ
特に50歳以下程度までの方は、1の毎月無理のない金額の積み立てを新NISAのつみたて投資枠で行うのが最も手間・手数料がかからず無難な含み益(長期的に平均すれば、年5~7%程度を目標)を確保できる方法でしょう。
つみたて投資枠の上限を超えて投資できる余裕がある方は、成長投資枠も1で行えば、最もシンプルで平均的な成果が出せるでしょう。
60代以上など、毎月のインカムを欲しい方は、成長投資枠では2も併用するのがよいでしょう。
いずれの投資手法も、短期的な株価の上下は気にする必要がありません。
また、いずれの手法も、暴落時にも淡々と投資を継続することで、特に効果が生じます。
したがって、自分にとって、暴落時にも淡々と投資を継続できる範囲の金額内で、信用取引やレバレッジを掛けたりせずに、現物取引のみで普段通りの投資を行うことが重要といえるでしょう。
と頭ではわかっていても、2020年の新型コロナショック時などと同様、今回も、暴落に慌てて狼狽売りをしてしまった方も多いかもしれません。
現在60歳の私(奥野)の場合、教科書的には、リスク資産(株式・株式投資信託等):安全性資産(現預金・日米国債等)の割合は、40%(100%-年齢):60%(年齢)程度を基準とするのがよいと言われることも多いです。
私の場合は、自身の性格等を勘案し、保守的に、リスク資産の割合をもっと少なめにし、現在のところリスク資産30%:安全性資産70%程度としています。
ちょうど1月ほど経ちましたので、8月上旬の暴落時に何をしたかをここで個人的に振り返ってみたいと思います。
1.つみたて投資枠
昨年まではつみたてNISAで月33,333円全世界株投信等の積立をしていましたが、本年1月からは新NISAのつみたて投資枠で全世界株投信を毎月10万円積み立て投資しています(クレカを活用してポイントを得られるようにしています)。
10万円×12か月×5年の最短で、つみたて投資枠への投資元本を600万円として、その後も運用を続ける予定です。
つみたて投資枠で今年から始めた全世界株投信は、8月2日までは含み益がそれなりに出ていましたが、8月5日は含み益がなくなり、わずかだけマイナスになっていました。
しかし、つみたて枠はとくに触る必要もないので、8月も自動的に10万円の積立がされ、数日で、含み益もプラスとなりました。
インデックス投信の長期積立は、投資期間の前半に暴落があると口数をたくさん買えることとなるため、15年~20年以上の長期投資をするつもりの方には望ましいことですので、積立をやめずに継続することが大事です。
(昨年までつみたてNISAで投資してきた全世界株投信等の積立分はそのまま放置して運用していますが、こちらは投資期間がある程度あったため、8月の暴落時も含み益がゼロになることはありませんでした)
2.成長投資枠
主に日本の大型安定高配当株・連続増配株に年240万円×5年間の最短で、成長投資枠の上限1,200万円を満たす予定です(昨年まで特定口座で買っていた日本や米国等の大型安定高配当株・連続増配株は、割安な時に買っていることもあり、成長投資枠へは移さず、特定口座で保有を続けています)
月平均20万円の個別株を投資するつもりでいましたが、1月からずっと日経平均が上がっており、狙っている銘柄もすべて割高でなかなか買い時が来ないまま7月末まで来ていました。
7月末までは、割高のためまとめ買いしたい銘柄はなかったため、割高度合いが少し低めの銘柄から選んで、単元未満株を少しずつ購入していましたが、7月末の時点で140万円(20万円×7か月)は買えていませんでした。
8月2日、5日と株価が大きく下げた時点で、狙っていた銘柄の株価が大きく下がり・配当利回りが4~5%に上がり、買い時を迎えたと判断しましたので、まとめて買いました(メガバンク、リース、商社、機械などの銘柄が狙い目と感じましたので、それらの銘柄をまとめ買いました)。
今年の成長投資枠の上限240万円はすぐに使い切ったため、特定口座でもまとめ買いしました。
その後購入した銘柄の株価はすべてすぐに上がりましたが、暴落時に安いところで高配当株・増配株を購入することで高利回りを確定させることが目的での購入ですので、含み益が増えてもそのまま持ち続けています。
高配当株・増配株投資も最近は人気ですが、割高な時に購入すると配当利回りも低くなりますし、少し株価が下がると含み損が出やすいです。
やはり、株価が高い時は、狙っている銘柄の研究をしながら、買うとしても小額の打診買いに留め、株価が大きく下がったときに、狙っている銘柄をまとめて購入することがポイントです。そうすることで、持ち株の配当利回り(取得利回り)も高くなり、含み損が生じる可能性も少なくなります。
アメリカの景気減速懸念からの株価下落の影響もあり、9月4日(水)にも日経平均株価が37,047円に下がり、(8月5日、2日に次ぐ、今年三番目の下落率だそうです)持ち株の中で買いたい水準に下がった銘柄がありましたので、ちょこちょこ買い増ししました。
9月5日(木)も日経平均は終値36,657円まで下がりました。
今後も株価は不安定な動きをする可能性がありますので、投資は自己責任で、株価が半額以下に落ち込んでもご自身のメンタルに影響が生じない範囲の余剰資金を用いて行うようにしましょう。
経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
- 電話で相談されたい代表取締役様は、有料電話相談のご予約をお願いします。
- 経営者様向け無料メール講座はこちら
所長の奥野です。
無料メール講座
(全国対応)
中小企業経営者様限定
60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!
無料メール講座登録はこちら
(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)