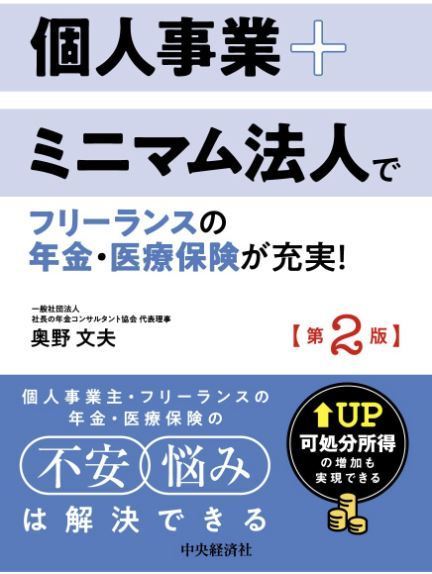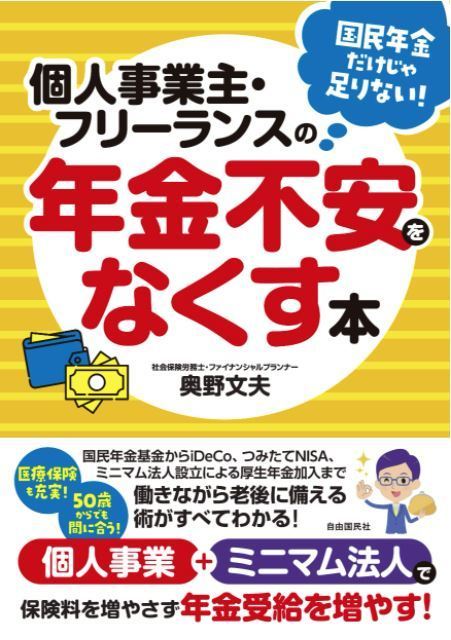60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
|---|
FAX | 077-578-8907 |
|---|
フリーランス(個人事業主)は厚生年金・健康保険に加入できないのでしょうか
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(案)が公表
(2021年1月8日)
2020年12月18日、政府は、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(案)を公表しました。
ガイドライン(案)には、
1.企業や仲介業者との契約では下請法や独占禁止法が適用され、一方的な報酬減額や納期変更は違法になること
2.実質的に雇用関係にある労働者と判断されれば、労働基準法等の労働関係法令が適用されること
などの内容が含まれています。
1月25日まで一般からの意見を公募した後、2021年度中の正式決定が見込まれています。
(ご参考)
・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(案)概要
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/dec/201224gl4.pdf
・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(案)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/dec/201224gl3.pdf
なお、上記2についてガイドラインには、形式的には請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、働き方の実態が労働基準法上の「労働者」に該当すると判断された場合は、労働基準法に定める労働時間や時間などのルールが適用されることになる、などの内容が記載されています。
このことは、ガイドラインでわざわざ定めるまでもなく当たり前のことで、現行法制度の内容を確認しているに過ぎません。
フリーランス・業務委託・請負等どのような名称で契約していようが、実態が労働基準法上の労働者に該当するのであれば、労働基準法等の労働関係諸法令が適用されるのは、当然のことです。
ガイドライン案には明記されてはいませんが、もし、労働基準法上の労働者に該当して賃金を受けているということになれば、労働者災害補償保険法に定められた政府労災保険の補償の対象ともなります。
そのうえ、もし、週所定労働時間20時間以上等の要件も満たしていれば、雇用保険にも加入することとなります。
なお、2021年1月から、従業員としての収入とフリーランス等による収入のどちらが多いかに関わりなく、要件を満たしていれば、雇用保険に加入することとなりました。
(ご参考)
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000776069.pdf
さらに、所定労働時間・所定労働日数ともに、その事業所の通常の従業員の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上であれば、70歳未満なら厚生年金に、75歳未満なら健康保険にも入ることとなります
ですから、フリーランスが、別途、どこかの事業所に従業員として勤務して上記の「4分の3以上」要件を満たして厚生年金・健康保険に加入するケースも中にはあるでしょう。
(社員数500人超の企業や、500人以下の企業でも労使の合意によって加入できる人の範囲を広げている企業に従業員として勤める場合は、「4分の3以上」要件を満たしていなくても、週所定労働時間20時間以上などの要件を満たせば厚生年金・健康保険に入れます)
(ご参考)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/1.pdf
法人代表者等役員として厚生年金・健康保険に加入することもできる
なお、書籍『個人事業+ミニマム法人でフリーランスの年金・医療保険が充実!』や『個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本』でも解説しました通り、わざわざ、他の事業所に従業員として一定時間以上雇われなくても、個人事業の全部または一部を法人化し、法人代表者等役員として経営に従事して法人から役員給与を受ければ、法人において厚生年金・健康保険に入れます。
法人代表者等役員と会社との関係は労働契約ではなく委任契約関係ですので、従業員の場合と異なり、所定労働時間や所定労働日数という概念はありません。
ですから、法人の経営に法人代表者等役員として従事し、法人から役員給与を受けていれば、70歳未満であれば厚生年金に、75歳未満であれば健康保険にも入れるのが基本です。
「4分の3以上」要件や「週20時間以上」要件は関係がありません。
(ご参考)
経営者、役員の社会保険加入条件について
経営者、役員の社会保険加入についての判断材料例はこちら
よくある質問への回答 他社の経営者から厚生年金・健康保険加入をすすめられました
(よくある質問)
ある会社の経営者から、「フリーランスでも厚生年金・健康保険に入れてあげる」と言われましたが、問題ないでしょうか。
(回答)
厚生年金・健康保険に加入できるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
1.法人役員に就任し、役員として経営に従事している実態があり、その会社から役員給与を受けている
2.厚生年金保険・健康保険の適用事業所の従業員として勤務し、所定労働時間および所定労働日数がその会社の通常の従業員の所定労働時間・所定労働日数の「4分の3以上」であり、
(社員数500人超の企業や、500人以下の企業でも労使の合意によって加入できる人の範囲を広げている企業の場合は、週所定労働時間20時間以上等の要件を満たしており、)
勤務実態もその通りであり、
その事業所から給与を受けている
(所定労働日数・所定労働時間とは就業規則や労働条件通知書に記載された勤務日数・勤務時間のことです)
まずは、その会社においてあなたが、上記1または2のいずれかの働き方をすることとなるのかをその会社に確認してみてください。
もし実際に、1または2のいずれかの働き方をするということであれば、その会社で厚生年金・健康保険に入っても「問題ない」といえます。
しかし、1・2のいずれにもあたらない場合は、会社は本来その人を厚生年金・健康保険被保険者とするための届出をすることができない筈ですので、問題があります。
実態として本来厚生年金・健康保険に加入できない人であるにも関わらず、形式的にだけ「法人役員として経営に従事して役員給与を受けている形で」、または、形式的にだけ「従業員として一定時間以上勤務して給与を受けている形で」加入させると言われても、関わらないようにするのがよいでしょう。
フリーランス・個人事業主向けの「脱法」「社会保険ビジネス」に注意
(2023年7月16日追記)
以前、上記の通り注意喚起したことがありますが、フリーランス向けの「脱法」「社会保険ビジネス」について、2023年6月26日の読売新聞で報道されていました。
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/feature/CO063816/20230625-OYTAT50056/
報道されていたような一般社団法人の理事に限らず、法人の役員として法人で健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を取得するためには、役員としてその法人の経営に従事して、その法人の役員としての労働の対償として報酬(役員給与)を受けている必要があります。
単に書類上、形式的に要件を満たしているだけではだめで、実態が要件を満たしていないといけません。
厚生年金保険や全国健康保険協会の健康保険(協会けんぽ)の被保険者となる際には、厚生年金保険・健康保険の適用事業所(会社)が、被保険者となる人について被保険者資格取得届を日本年金機構(年金事務所)に提出する必要があります。
日本年金機構では、法人理事が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるかどうかの主な判断材料例を疑義照会回答において、次の通り公表しています。
・当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
・当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
・当該法人の役員会等に出席しているかどうか
・当該法人の役員への連絡調整または職員に対する指揮監督に従事しているかどうか
・当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
・当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか
これらの判断材料例などを参考にして、それぞれの事案ごとに実態を踏まえて判断されることとなっています。
被保険者となる要件を満たしていないのに被保険者資格取得届を提出することは違法であり、法律上罰則も設けられています。
(税金などもそうですが)健康保険・厚生年金保険に関しても、実態として法律で定められた(または法律が想定している)要件を満たしていないにもかかわらず、単に形式を取り繕っているだけの事案があることが確認できた場合、厚生労働省は、そのような手法を採用しても効果が生じなくなるように、通達を出して取り扱いを明確化することが一般的です。
(過去には例えば、実体のない海外法人活用、賞与を分割支給する手法など、一部コンサルティング会社が有料サービスとしてサポートしていたような脱法的な手法を採っても効果が生じないように、取り扱いを明確化してきました)
それ以前に、そもそも、フリーランス・個人事業主となる人は、寄らば大樹の陰という考え方が
合わず、独立独歩、自分の好きにやっていきたい、という人も多いのではないでしょうか。
それなのに、わざわざ自分と関係のない他者が設立した関係のない法人の、自分がよく把握していない事業に加盟料を払ってまで参画して、役員として法律で課されている法的責任リスクを負う必要は全くないように思います。
自分が役員となっている会社の財務状況・経営状況・運営状況や他にどんな役員が何人いるのか、各役員の人となり・実績なども確認せずに、役員という法的責任の大きな立場を引き受けることを検討する必要はないでしょう。
事業経営・業務運営によって生じるメリットもデメリットもすべて自分が責任を負う、との意思で自ら法人を設立するのではなく、自分がコントロールできない法人が自分の運命をいつ左右するかもわからない、という不安な状態にわざわざ陥る必要もないと思うのですね。
メリットがあるからというだけで、どんなデメリットがありうるのかを一切考慮せずに利用する、という判断は、事業経営においても日常生活においても普通はあまりしないと思うのですが‥‥
どうか、目先の経費節減だけにとらわれて加担することのないようご注意いただきたいところです。
最近は、自社の理事(役員)として外部のフリーランス・個人事業主を健康保険・厚生年金保険に加入させるのではなく、自社のサービスを利用できる会員を自社の従業員として健康保険・厚生年金保険に加入させる事例について相談を受けることもあります。
こちらも法律上は、その会社の従業員としての勤務実態やその会社の従業員としての労働の対償としての会社からの報酬(給与)支払実態がなければ、健康保険・厚生年金保険の被保険者になれないことは同じです。
(役員の場合と異なり、従業員の場合は所定労働時間・所定労働日数によって健康保険・厚生年金保険に加入できる基準が定められています。現在は100人以下の企業においては、1週の所定労働時間・1月の所定労働日数がともに、その会社の常時雇用従業員の1週の所定労働時間・1月の所定労働日数の4分の3以上であることが被保険者となるための要件です)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html
政府労災保険への特別加入の対象業種が拡大予定
政府労災保険は、従業員として働いている人が業務でケガをしたり病気になったりしたときに、治療費や休業補償などが給付される制度です。
全額企業負担の労災保険料でまかなわれています。
個人事業主・フリーランスは、政府労災の対象とならないのが原則です。
しかし、建設業の一人親方など、従業員でない人の中にも例外的に自身で労災保険料を負担して政府労災保険に加入できる人もいます(特別加入といいます)。
この政府労災保険への特別加入について、次の3つの業種が2021年度にも対象に加えられる見込みです。
・芸能従事者(218,250人)
・アニメーション制作従事者(推計10,000人)
・柔道整復師(73,013人)
カッコ内の数字は、全就業者数です。
業務でのけが・病気が多く発生している、組織運営方法等が整備された業界団体があり労災保険事務の処理ができる体制がある等の理由から、まずはこれらの3業種について特別加入が適用されることとなりました。
詳細については、今後の公表をお待ちください。
なお、今後さらに対象業種を増やすかどうかについても、実態を踏まえて検討を続けられる見込みです。
また、「65歳以降70歳までの従業員の就業機会確保措置」が2021年度から企業の努力義務となります。
この措置としては、定年引上げ・継続雇用制度の導入・定年廃止以外に、労使で合意した上での雇用以外の「創業支援等措置」(継続的に業務委託契約を締結する制度や継続的に社会貢献活動に従事できる制度)も認められることとなっています。
65歳以降70歳までの間これらの創業支援等措置によって働く人(65歳までの会社員経験を活かして講師や事務職として働く人などが多くなるのではないかと想定されています)のうち、常態として労働者を使用しないで作業を行う人を特別加入制度の対象とすることについても、検討されています。
(ご参考)労災特別加入対象者拡大についての最近の議論内容については、厚生労働省ホームページで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126970.html
フリーランス ガイドラインのパンフレットが公表されました
2021年3月26日に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が策定されました。
このガイドラインについては、案が出された段階でご案内しましたが、イラスト入りでガイドラインについて解説しているパンフレットも公表されましたので、下記にご案内いたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/000766340.pdf
策定されたガイドライン本文や概要は、こちら
(ガイドライン)
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000759477.pdf
(ガイドライン 概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000759478.pdf
また、ガイドライン案に対して寄せられた国民の意見と、
それに対する国の考え方も公表されています。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210326free01.pdf
この中で、社会保険等に関する意見としては、例えば、次のような意見が寄せられたとのことです。
「フリーランスとして自力で事業を持続化していきたいとの思いに答えられるよう、社会保険や労働保険の恩恵を受けることが少ない状況を踏まえ、社会保障政策の不備を補充・補填してほしい。」
それに対する国の考え方としては、次のように示されています。
「社会保険については、フリーランスの方々への保障のあり方を考えていくという視点も重要である一方で、保険料を賦課する報酬や保険料負担・納付を行う者の定義など、従来の被用者保険にはない困難な論点があることから、働き方の多様化の広がりや労働政策の動向なども踏まえ、多様な働き方に対応した保障の在り方を検討していくこととしております。」(以下省略)
ここで述べられているのは、これまでにも様々なところで繰り返し説明されてきたのと同様の内容となっています。
既にご案内しました通り、2021年度からごく一部の業種のフリーランスの方も新たに労災保険の特別加入の対象となりました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf03f1249c3ec1b65370589b7dc1f83af56859f2
しかし、それ以外の社会保険・年金制度については、フリーランス関連の大きな改正は今のところありません。
フリーランス・トラブル110番サイト
また、厚生労働省より東京第二弁護士会が受託して「フリーランス・トラブル110番」が運営されています。
https://freelance110.jp/
フリーランス・個人事業主の方が契約や仕事上のトラブルでお悩みの場合、電話(フリーダイヤル)や問い合わせフォームで無料で相談できます(匿名可)。
必要に応じ、対面(東京都新宿区)もしくはビデオ通話での相談もできます。
労災保険特別加入の対象者がさらに拡大
●令和3年4月から、次の3業種の個人事業主等も新たに政府労災保険に特別加入することができるようになっています。
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者
・柔道整復師
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html
●令和3年9月1日からは、以下の方について新たに特別加入制度の対象となりました。
・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ ITフリーランス
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html
●令和4年4月から労災特別加入できる人がさらに増えました。
令和4年4月から、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師について、個人事業主でも政府労災への特別加入ができる対象に加えられました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00006.html
政府はフリーランスへの労災保険の適用拡大の方針を示しており、特別加入の対象として令和3年4月にはアニメーション制作従事者や芸能従事者、柔道整復師が、さらに同年9月にはITフリーランスや自転車配達員が追加されましたが、さらに対象となる人が令和4年4月から増えました。
●さらに、令和4年7月からは、フリーランスとして働く歯科技工士も一人親方として労災保険に特別加入できるように改正される予定です。
インボイス制度 特設サイトがリニューアル
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
令和3年10月1日から登録申請書の提出が可能となるため、国税庁のインボイス制度特設サイトもリニューアルされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
上記特設サイトでは、オンライン説明会や、インボイス制度電話相談センターの電話番号なども記載されています。
国民健康保険料の上限の引き上げ予定について
(202211月11日)
報道されていました通り、国民健康保険料について、来年度から年間上限額を今より2万円引き上げ、年間104万円とされる見込みです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221028/k10013873691000.html
国民健康保険料の年間上限額は、2021年度は99万円でしたが、2022年度は102万円に引き上げられていました。
これが、2023年度はさらに104万円に引き上げられるということで、
・個人事業のみで働く人
・個人事業を営みながら、厚生年金保険の強制適用事業所
ではない事業所でも働いて給与を受けている人
・個人事業を営みながら、別の事業所でも厚生年金保険の被保険者となれない条件で働いて給与を受けている人
等で、所得の多い方にとっては、手取りが少なくなる方向の改正となります。
今後はミニマム法人活用がさらに注目されるかもしれません。
令和7年(2025年)年金法改正に向けての議論
令和6年(2024年)に予定されている公的年金の財政検証や、令和7年(2025年)に予定されている年金法改正に向けて、社会保障審議会年金部会が開催されました。
(2022年10月25日に第1回開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html
・国民年金(基礎年金)の保険料を納める期間を40年(20歳~59歳)から45年(20歳~64歳)に5年間延期するのがよいのではないかという案
・現在厚生年金に加入できない以下人たちも厚生年金保険に強制加入とするのがよいのではないかという案
等について、これから具体的な議論が開始される予定です。
(実際に2025年改正にこれらの案が盛り込まれるかは、現時点ではわかりません)
今回に限らず、年金改正が話題になったときはいつもよくあることなのですが、インターネット上等で、改正案の内容を正しく伝えていない記事が散見されます。
その結果、特に若い世代で年金制度について誤解している人が書いた、根拠のない意見が多く拡散されています。
・国民年金(基礎年金)の保険料を納める期間を40年(20歳~59歳)から45年(20歳~64歳)に5年間延期するのがよいのではないかという案
についても
・現在厚生年金に加入できない以下人たちも厚生年金保険に強制加入とするのがよいのではないかという案についても、
将来の年金給付水準維持の効果がある、つまり、改正案を実施しないままの場合に比べて、改正案を実施した場合の方が、将来年金を受給する人たちの年金の給付水準が
高くなるのですが(このことは、2019年の財政検証結果報告の際に国が示した「オプション試算」で明らかにされています)、
まさに恩恵を被る世代である若い人たちが、保険料負担が増える人が出て来る点のみを強調した記事を目にすることで、「年金保険料を払うのは無駄だ・損だ」などの誤解をして、国民年金保険料を納めるのをやめてしまうようなことがあるとすれば、大変残念で、もったいないことだと思います。
年金・社会保険については、人の意見に反射的に影響を受けるのではなく、公表されているデータや資料を踏まえて、一人ひとりが自身の理想の人生・働き方実現のための
正しい選択をしていくことが重要だと思います。
(厚生年金保険)子の養育期間中の標準報酬月額の特例措置について
(2023年8月9日)
厚生年金保険の被保険者となっている人には、子どもが3歳に達するまでの養育期間中に勤務時間短縮などにより標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、その子どもを養育する前の標準報酬月額に基づいて将来受け取る年金額を計算してくれる特例措置(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)があります。
該当する被保険者が申し出ることにより、特例が適用されます。
この特例が適用される人は、
・保険料については、低下した標準報酬月額に基づく保険料を払えばよいのですが、
・将来もらえる年金額を計算する際には、標準報酬月額が低下しなかったものとして(つまり、低下前の標準報酬月額で働いたものとして)年金額を計算してもらえます。
この特例は、厚生年金保険の被保険者であれば活用できますので、従業員だけでなく、代表取締役・取締役等法人の役員も対象となり得ます。
女性の被保険者だけでなく、男性被保険者も対象となり得ます。
若い世代のミニマム法人役員さんは、こういう制度があることを知っておかれてもよいかもしれません。
(注)この特例は厚生年金保険の制度ですので、健康保険の保険給付の額は、低下後の標準報酬月額によって計算されます。
(参考:日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
詳しくは、管轄の年金事務所にご照会ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/index.html
経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
- 電話で相談されたい代表取締役様は、有料電話相談のご予約をお願いします。
- 経営者様向け無料メール講座はこちら
所長の奥野です。
無料メール講座
(全国対応)
中小企業経営者様限定
60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!
無料メール講座登録はこちら
(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)